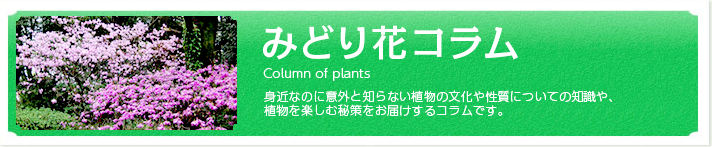
伊豆七島の八丈島、三宅島、御蔵島に自生するシマテンナンショウはサトイモ科テンナンショウ属の植物で、鳥足状の2枚の大きな葉と緑の仏炎苞を持ちます。テンナンショウの仲間は地下に球茎を持ちますが、この中にはシュウ酸カルシウムの針状結晶を含み、食べると口の中が腫れ上がり大変なことになるといわれています。
ところが八丈島ではシマテンナンショウの球茎を食用としたと本で読んだことがあり、どうやって食べるのか長年疑問でした。
その後、何度か春に八丈島に行く機会があり、島の植物観察をしたり、西山(八丈富士)、東山(三原山)に登ったりと島を散策すると、至る所にシマテンナンショウが生えているのを見ました。道の脇にも山の中にもどこに行っても緑の仏炎苞から長い付属体を伸ばした姿を数多く見ることができるのです。
八丈島は東京から南に290キロ離れた島で、黒潮の影響で冬も暖かい場所で、昔は流人の島とも呼ばれ、江戸時代には春秋2回流人を運ぶ船が着き、何人もの罪人が村々に振り分けられていたそうです。
この頃は何度もの凶作や飢饉が島を襲い、島民は飢餓に苦しめられ、自分たちも食べていくのがやっとだったようで、700余人もの餓死者をだしたという記録も残っています。

流人が一つ一つ海岸から運んだ石で積み上げたという
玉石垣
ところでシマテンナンショウはどうやって食べられていたのでしょうか?
長年の疑問を民宿のご主人に聞いてみると、ちょうど遊びに来ていたご主人の同級生という方が「俺は食べたことがあるよ。」というので、早速教えてもらうことができました。
シマテンナンショウは島ではヘンゴダマと呼ばれていますが、この球茎を掘ってきて洗い、蒸すか茹でるかして皮をむきます。これを臼に入れて搗いて餅状にして食べるそうです。私が「何も下処理をせずに食べるのですか?」とびっくりして聞くと、その方は笑いながら「食べ方があるんだよ。」と言われました。それは餅状になったヘンゴダマを千切って小さく丸め、顔を上に向けてこれをのどに落とし込むという何とも恐ろしい食べ方でした。味をかみしめるのではなく、お腹にたまればよい、それで飢えを忘れるのです。私はその話を聞いたとき、しばし絶句し、この島で暮らしてきた人々の生活の厳しさをほんの少しですが垣間見ることができました。
ヘンゴダマは飢えとの戦いの中で培われてきた食文化なのだと・・・
島にはテンナンショウの仲間は他にマムシグサとウラシマソウが自生していましたが、その方は「食べられるのはヘンゴダマだけだ。」と言っていました。多分、シマテンナンショウは他の二種に比べてシュウ酸カルシウムの含有量が少ないのではないのでしょうか。
八丈島の歴史のひとこまに植物を通して触れることができた旅でした。
緑花文化士 臼井治子
(2021年3月掲載)

ギンドロ 松井恭
植物標本の作製で気づいたこと 小林正明
イチゴノキはヤマモモにそっくり 古川克彌
チューリップの思い出 柴田規夫
稲刈り月間 田中由紀子
夏野菜のズッキーニ 米山正寛
サイカチ(皁角子) 松井恭
菜の花の見直し 逸見愉偉
カラスノエンドウ(烏野豌豆)の話 豊島秀麿
絶滅危惧種トチカガミが教えてくれたこと 小林正明
桃の節句、モモ、そしてヤマモモ 森江晃三
もっとツツジを! 鈴木 泰
野山の手入れと草木染め 福留晴子
キチジョウソウ 横山直江
旅と植物 日名保彦
ナギの葉 松井恭
雑木林~私の大好きな庭 千村ユミ子
名札の問題 逸見愉偉
ミソハギ ~盆の花~ 三輪礼二郎
葛粉についてもっと知りたくて 柴田規夫
明治期にコゴメガヤツリを記録した先生 小林正明
「ムラサキ」の苗を育てる 服部早苗
活躍広がる日本発のDNA解析手法 植物の”新種”報告がまだまだ増えそう! 米山正寛
地に咲く風花 セツブンソウ 田中由紀子
クリスマスローズを植物画で描く 豊島秀麿
カラムシ(イラクサ科) 福留晴子
園芸と江戸のレガシー 鈴木泰
植物標本作りは昔も今もあまり変わらず 逸見愉偉
カポックの復権 日名保彦
オオマツヨイグサ(アカバナ科) 横山直江
森の幽霊? ギンリョウソウ 三輪礼二郎
ジャカランダの思い出 松井恭
水を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
都市緑化植物と江戸の園芸 鈴木泰
スノードロップの季節 服部早苗
枯れるオオシラビソ 蔵王の樹氷に危機 米山正寛
シモバシラ 森江晃三
琥珀 松井恭
うちの藪は深山なり 千村ユミ子
神社で出会った木々 田中由紀子
光を効率よく求めて生きるつる植物 柴田規夫
モッコウバラとヒマラヤザクラ 服部早苗
志賀直哉と赤城の
花の
桜の園芸文化 鈴木泰
動物を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
お餅とカビ 森江晃三
危ない!お豆にご用心 川本幸子
風を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
山椒の力 いつも緑のとまと
土佐で見たコウゾの栽培 米山正寛
大伴家持の愛した花 カワラナデシコ 安田尚武
「シアバターノキ」とブルキナファソ 松井恭
白い十字の花、ドクダミの魅力 柴田規夫
いずれアヤメか 三輪礼二郎
すみれの花咲く頃 川本幸子
シマテンナンショウの話 臼井治子
セツブンソウ(節分草) 森江晃三
ハイジとアルプスのシストの花 松井恭
年賀状 再び 永田順子
開閉するマツカサ 小野泰子
和の色、そして、茜染めの思い出 柴田規夫
知らないうちに 逸見愉偉
ボタニカル・アートのすすめ 日名保彦
ハマナスの緑の真珠 志田隆文
恋する植物:テイカカズラ 古田満規子
マメナシを知っていますか? 服部早苗
桜を植えた人 伊藤登里子
春の楽しみ 鯉渕仁子
みゆちゃんのわすれもの 山岸文子
遅くなってゆく年賀状 永田順子
イソギクは化石のかわりに 古川克彌
イノコズチの虫こぶ 清水美重子
ヒマラヤスギの毬果 小野泰子
私たちのくらしと海藻 川本幸子
河童に会いに 松井恭
カラスビシャクを観察して 志田隆文
何もかも大きい~トチノキ~ 三輪礼二郎
キンラン・ギンラン 横山直江
早春の楽しみ 豊島秀麿
キンセンカ、ホンキンセンカ 佐藤久江
カラスウリの魅力 小林正明
イチョウ並木と精子 森江晃三
コスモスに秘められた物語 下田あや子
「蟻の火吹き」の語源について 志田隆文
新しい植物分類 豊島秀麿
サルスベリ(猿滑、百日紅) 宮本水文
小松原湿原への小さな旅 松村文子
野生植物の緑のカーテン 小林英成
江戸の文化を伝えるサクラソウ 黒子哲靖
工都日立のさくら物語 ―大島桜と染井吉野― 鯉渕仁子
ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属) 佐藤久江
能楽と植物 川本幸子
サカキの冬芽と花芽 古川克彌
ケンポナシみつけた 永田順子
セイダカアワダチソウの話 逸見愉偉
ヒガンバナ、そしてふるさと 森江晃三
いにしえの薬草‘ガガイモ’ 服部早苗
トリカブトの話し 三輪礼二郎
ツユクサ、花で染めても色落ちしてしまう欠点を逆利用!柴田規夫
アサギマダラ 横山直江
「思い込み」の桜 田中由紀子
常磐の木 タチバナ 清水美重子
柿とくらし 三島好信
植物に親しむ 小林正明

























