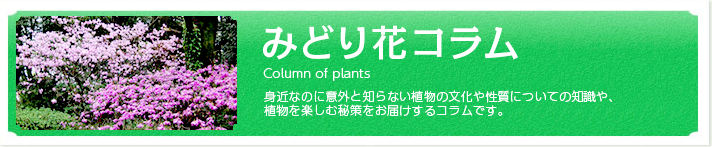
夏も終わりを迎える頃、藪や道路わきの植え込みにからまった蔓に、ガガイモの花が咲きだします。綿毛に覆われたピンクの5弁の花の集まりが、まるで小さな花束のよう!花粉を運んでくれるマルハナバチや、ツチバチを呼ぶためか、強い香りを放ちます。
晩秋になると紡錘形の実が裂けて、絹糸のような‘種髪’をつけたタネが一つずつ、ふんわりと旅立ちます。タネがすべて旅立った後の実は、まるでカヌーのようです。
古名をカガミグサと言い、漢方では強壮剤に用いたり、生の茎葉を解毒や腫物治療に用いたそうです。古事記によれば、「スクナビコナノミコト」という薬草を司る小さな小さな神様(一寸法師のモデルという説も。)が「天之蘿摩船」(あまのかがみのふね、ガガイモの実のこと)に乗って波がしらを伝って日本においでになり、「大国主の神」の国造りを助けられたとか。
渡りをする蝶として有名な「アサギマダラ」(タテハチョウ科マダラチョウ亜科)の食草は、イケマ、オオカモメヅル、キジョランなど(すべて旧ガガイモ科)ですが、時にはガガイモを食草とすることもあるそうです。ガガイモの仲間には毒があり、アサギマダラはその毒を体に取り込むことで、天敵の鳥から身を守っているのです。アサギマダラも、ガガイモを薬草として利用しているんですね!
ガガイモ科はDNA鑑定により、キョウチクトウ科にまとめられました。沖縄や台湾には、マダラチョウ亜科の蝶で唯一、以前からキョウチクトウ科の「ホウライカガミ」を食草とする「オオゴマダラ」がいます。人間が研究するよりずっと以前から、ガガイモもホウライカガミも同じ仲間だと、チョウたちは知っていたんですね。あっ、もしかしたら、いにしえの人たちも知っていたのかな?カガミグサとホウライカガミが同じ仲間だと!
緑花文化士 服部早苗
(2017年8月2日掲載)

ギンドロ 松井恭
植物標本の作製で気づいたこと 小林正明
イチゴノキはヤマモモにそっくり 古川克彌
チューリップの思い出 柴田規夫
稲刈り月間 田中由紀子
夏野菜のズッキーニ 米山正寛
サイカチ(皁角子) 松井恭
菜の花の見直し 逸見愉偉
カラスノエンドウ(烏野豌豆)の話 豊島秀麿
絶滅危惧種トチカガミが教えてくれたこと 小林正明
桃の節句、モモ、そしてヤマモモ 森江晃三
もっとツツジを! 鈴木 泰
野山の手入れと草木染め 福留晴子
キチジョウソウ 横山直江
旅と植物 日名保彦
ナギの葉 松井恭
雑木林~私の大好きな庭 千村ユミ子
名札の問題 逸見愉偉
ミソハギ ~盆の花~ 三輪礼二郎
葛粉についてもっと知りたくて 柴田規夫
明治期にコゴメガヤツリを記録した先生 小林正明
「ムラサキ」の苗を育てる 服部早苗
活躍広がる日本発のDNA解析手法 植物の”新種”報告がまだまだ増えそう! 米山正寛
地に咲く風花 セツブンソウ 田中由紀子
クリスマスローズを植物画で描く 豊島秀麿
カラムシ(イラクサ科) 福留晴子
園芸と江戸のレガシー 鈴木泰
植物標本作りは昔も今もあまり変わらず 逸見愉偉
カポックの復権 日名保彦
オオマツヨイグサ(アカバナ科) 横山直江
森の幽霊? ギンリョウソウ 三輪礼二郎
ジャカランダの思い出 松井恭
水を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
都市緑化植物と江戸の園芸 鈴木泰
スノードロップの季節 服部早苗
枯れるオオシラビソ 蔵王の樹氷に危機 米山正寛
シモバシラ 森江晃三
琥珀 松井恭
うちの藪は深山なり 千村ユミ子
神社で出会った木々 田中由紀子
光を効率よく求めて生きるつる植物 柴田規夫
モッコウバラとヒマラヤザクラ 服部早苗
志賀直哉と赤城の
花の
桜の園芸文化 鈴木泰
動物を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
お餅とカビ 森江晃三
危ない!お豆にご用心 川本幸子
風を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
山椒の力 いつも緑のとまと
土佐で見たコウゾの栽培 米山正寛
大伴家持の愛した花 カワラナデシコ 安田尚武
「シアバターノキ」とブルキナファソ 松井恭
白い十字の花、ドクダミの魅力 柴田規夫
いずれアヤメか 三輪礼二郎
すみれの花咲く頃 川本幸子
シマテンナンショウの話 臼井治子
セツブンソウ(節分草) 森江晃三
ハイジとアルプスのシストの花 松井恭
年賀状 再び 永田順子
開閉するマツカサ 小野泰子
和の色、そして、茜染めの思い出 柴田規夫
知らないうちに 逸見愉偉
ボタニカル・アートのすすめ 日名保彦
ハマナスの緑の真珠 志田隆文
恋する植物:テイカカズラ 古田満規子
マメナシを知っていますか? 服部早苗
桜を植えた人 伊藤登里子
春の楽しみ 鯉渕仁子
みゆちゃんのわすれもの 山岸文子
遅くなってゆく年賀状 永田順子
イソギクは化石のかわりに 古川克彌
イノコズチの虫こぶ 清水美重子
ヒマラヤスギの毬果 小野泰子
私たちのくらしと海藻 川本幸子
河童に会いに 松井恭
カラスビシャクを観察して 志田隆文
何もかも大きい~トチノキ~ 三輪礼二郎
キンラン・ギンラン 横山直江
早春の楽しみ 豊島秀麿
キンセンカ、ホンキンセンカ 佐藤久江
カラスウリの魅力 小林正明
イチョウ並木と精子 森江晃三
コスモスに秘められた物語 下田あや子
「蟻の火吹き」の語源について 志田隆文
新しい植物分類 豊島秀麿
サルスベリ(猿滑、百日紅) 宮本水文
小松原湿原への小さな旅 松村文子
野生植物の緑のカーテン 小林英成
江戸の文化を伝えるサクラソウ 黒子哲靖
工都日立のさくら物語 ―大島桜と染井吉野― 鯉渕仁子
ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属) 佐藤久江
能楽と植物 川本幸子
サカキの冬芽と花芽 古川克彌
ケンポナシみつけた 永田順子
セイダカアワダチソウの話 逸見愉偉
ヒガンバナ、そしてふるさと 森江晃三
いにしえの薬草‘ガガイモ’ 服部早苗
トリカブトの話し 三輪礼二郎
ツユクサ、花で染めても色落ちしてしまう欠点を逆利用!柴田規夫
アサギマダラ 横山直江
「思い込み」の桜 田中由紀子
常磐の木 タチバナ 清水美重子
柿とくらし 三島好信
植物に親しむ 小林正明
























