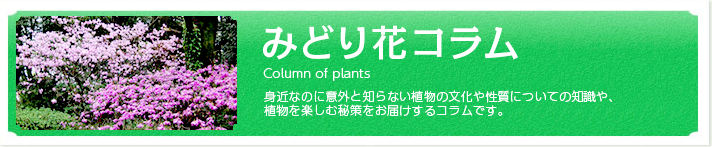
日本では、江戸時代にハナショウブやサクラソウ、サクラ、ツツジなど多くの園芸植物が発展しました。これらの伝統的な園芸植物について、あるベテラン園芸家は、日本のハナショウブやサクラソウとヨーロッパ産のジャーマンアイリスやプリムラ・オーリキュラを比較して「日本では個々の自生植物を徹底的に追及してその実生を繰り返し、差異を調べて、新品種を作り」「西洋では原種の複雑な交配や交雑種によって新品種を生み出している」と書いています。
なぜハナショウブ、サクラソウなどは1種類の中での実生が繰り返されてきたのでしょうか?実は現在でもこれらは同属の他種ととても交雑しにくい植物です。サクラソウは日本国内に同属のクリンソウ、カッコソウ、オオサクラソウなどがありますが、自然交雑種は発見されず、人工でも胚培養などの技術を使わないと交配できないようです。ハナショウブもヨーロッパ産のキショウブとの交配が近年実現しているだけで、アヤメ、カキツバタ、ヒオウギアヤメなどの日本産の原種同士の交配は自然状態では非常にまれです。種間交配を「しなかった」のではなく「できなかった」のです。東アジアや東欧に多いBearded iris(ジャーマンアイリスの仲間)は種間交配が容易で、人為交配の開始以前に自然や栽培下で多くの雑種が生じていたことが知られています。プリムラ・オーリキュラも雑種起源で、最初は自然交雑種とそのランダムな実生から園芸化が始まったと思われます。
その他、外来種であるアサガオは国内に交配できる同属のものがなかったこと、同じく梅、キク、シャクヤク、ボタンなどははじめから高度に改良された種が渡来し、国内産の同属原種はいずれも花が小さく大輪性を求める育種の方向性にふさわしくなかったからではないでしょうか。キクではイソギクなどとの自然交雑が知られていますが、園芸的な価値は認められなかったようです。これらの渡来植物も日本で大いに発展しました。
実際には、日本産でも雑種ができやすい植物では、交雑種が大いに利用されてきました。ツバキでは、近年になって桃山時代に作出されたとされる『有楽』が中国産のピタールツバキとの雑種であることが明らかになりました。
-300x300.jpg)
ツバキ『有楽』
また、ツバキの園芸品種の多くはヤブツバキとユキツバキとの交雑により生み出されたと推定されています。ヤブツバキとユキツバキが別種なのか亜種なのか、見解は分かれますが、「形態的には別種とみなすほど差があるが、生殖的には分かれていない」と考えていいのではないでしょうか。
同じツバキ属のサザンカの仲間では、原種からの選抜のほか、ヤブツバキとの交雑種カンツバキ、ハルサザンカが江戸時代から知られ、サザンカの仲間として明治時代以降現代までさらに大きな発展をしました。
サクラでは、18世紀初めの花壇地錦抄に46品種の記載があることなどから、江戸時代の初期には既に多数の品種があり、幕末にはその数倍に達していたようです。サトザクラの多くはヤマザクラとオオシマザクラの交雑種であり、その他マメザクラ、カスミザクラ、エドヒガン、チョウジザクラなどの種間交雑が報告されています。
ツツジでは17世紀から「霧島つつじ」が知られていますが、これはヤマツツジとミヤマキリシマの交雑種と推定されています。その後、さらにサタツツジ・モチツツジ・キシツツジなどとの交雑、中国や琉球列島産の原種の関与が考えられる大輪のリュウキュウ系品種が発展し、幕末には今日のツツジの品種群が成立したようです。リュウキュウ系のオオムラサキや幕末から育種されたクルメツツジなどは、現在でも大量に使用される緑化樹木となっています。

ホンキリシマ
ツバキの他にも、サクラでは琉球/中国産のカンヒザクラが用いられていて、これら主要花木ではすべて当時の海外産原種との雑種があることになります。
欧米では早くから日本の園芸植物を高く評価し、開国以前からのシーボルトによる幅広い野生や園芸植物の収集を始め、明治時代には斑入り植物やキク、ツツジ、ハナショウブなどが輸出され、イギリスへのイングラムによる多様なサクラの導入もありました。

江戸菊
-300x225.jpg)
花菖蒲「宇宙(菖翁花)」
現在、世界中の園芸植物で、原種の樹高が10m以上にもなる花木で100以上の品種があるものはサクラ、ツバキだけであり、その大部分が江戸時代からの品種です。西欧の代表的な花木である低木のバラでさえ、19世紀以前の品種は極めて限られています。西欧中心に改良された花木で、ある程度の品種があるものは、バラを除けば19世紀からのシャクナゲ、20世紀後半からのマグノリアぐらいです。古くからの果樹のスモモやリンゴでも、花を観賞するものは、ツバキやサクラ、ウメなどに比べればわずかな種類しかありません。近年、ツバキやサクラでは欧米で新品種が作出されていますが、その多くの基礎になっているのは日本の原種や伝統品種です。さらに低木のツツジ、観葉樹木のカエデ類も合わせると江戸のレガシーが世界の庭園や都市を彩っているのです。
開国期(1860年前後)には、既に主要な花卉の改良が進んでいた日本に比べ、欧米ではバラ、ダリア、アイリスなどの品種改良がやっと始まった時代でした(バラでは1800年代初め、ダリアでは八重咲は1800年代初め、ポンポン咲きは1829年、カクタス咲きが1874年頃に出現、ジャーマンアイリスの近代的な育種が始まったのが1820年頃)。既に高度に改良された園芸品種が多数あった日本は、欧米人にとって驚異的だったのでしょう。

カクタス咲きダリア
(小金井公園にて撮影)
.jpg)
アイリス 「ヴァニティ」
江戸時代の園芸品種がどのようにして生み出されたか、その実態は明らかになっていません。おそらく植木屋、武家屋敷などには自然や栽培下で生じた鑑賞価値が高いものが集められ、さらに海外から導入されたものも加わって生じた多様性に満ちた集積ができて、そこから、実生でより変わったものが生まれ、さらに実生や選別が繰り返されたのではないでしょうか。
このような旧式の育種を、欧米の技術を学んだ専門家が非科学的として退けた明治の文明開化の時代に「日本は単一種、海外は種間交配」という説ができたようです。それが現在でも実態に反して通用しているのではないでしょうか。
江戸時代の日本は複数の原種の交雑による品種の作出でも最先端でした。「近代科学的手法ではないけれども有効だった」、日本の園芸の歴史を、例えば近代医学に対する漢方医学のようなものとして見直してみる必要があるのではないでしょうか。
緑花文化士 鈴木 泰
(2023年10月掲載)

サイカチ(皁角子)
菜の花の見直し 逸見愉偉
カラスノエンドウ(烏野豌豆)の話 豊島秀麿
絶滅危惧種トチカガミが教えてくれたこと 小林正明
桃の節句、モモ、そしてヤマモモ 森江晃三
もっとツツジを! 鈴木 泰
野山の手入れと草木染め 福留晴子
キチジョウソウ 横山直江
旅と植物 日名保彦
ナギの葉 松井恭
雑木林~私の大好きな庭 千村ユミ子
名札の問題 逸見愉偉
ミソハギ ~盆の花~ 三輪礼二郎
葛粉についてもっと知りたくて 柴田規夫
明治期にコゴメガヤツリを記録した先生 小林正明
「ムラサキ」の苗を育てる 服部早苗
活躍広がる日本発のDNA解析手法 植物の”新種”報告がまだまだ増えそう! 米山正寛
地に咲く風花 セツブンソウ 田中由紀子
クリスマスローズを植物画で描く 豊島秀麿
カラムシ(イラクサ科) 福留晴子
園芸と江戸のレガシー 鈴木泰
植物標本作りは昔も今もあまり変わらず 逸見愉偉
カポックの復権 日名保彦
オオマツヨイグサ(アカバナ科) 横山直江
森の幽霊? ギンリョウソウ 三輪礼二郎
ジャカランダの思い出 松井恭
水を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
都市緑化植物と江戸の園芸 鈴木泰
スノードロップの季節 服部早苗
枯れるオオシラビソ 蔵王の樹氷に危機 米山正寛
シモバシラ 森江晃三
琥珀 松井恭
うちの藪は深山なり 千村ユミ子
神社で出会った木々 田中由紀子
光を効率よく求めて生きるつる植物 柴田規夫
モッコウバラとヒマラヤザクラ 服部早苗
志賀直哉と赤城の
花の
桜の園芸文化 鈴木泰
動物を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
お餅とカビ 森江晃三
危ない!お豆にご用心 川本幸子
風を利用してタネを散布する植物 柴田規夫
山椒の力 いつも緑のとまと
土佐で見たコウゾの栽培 米山正寛
大伴家持の愛した花 カワラナデシコ 安田尚武
「シアバターノキ」とブルキナファソ 松井恭
白い十字の花、ドクダミの魅力 柴田規夫
いずれアヤメか 三輪礼二郎
すみれの花咲く頃 川本幸子
シマテンナンショウの話 臼井治子
セツブンソウ(節分草) 森江晃三
ハイジとアルプスのシストの花 松井恭
年賀状 再び 永田順子
開閉するマツカサ 小野泰子
和の色、そして、茜染めの思い出 柴田規夫
知らないうちに 逸見愉偉
ボタニカル・アートのすすめ 日名保彦
ハマナスの緑の真珠 志田隆文
恋する植物:テイカカズラ 古田満規子
マメナシを知っていますか? 服部早苗
桜を植えた人 伊藤登里子
春の楽しみ 鯉渕仁子
みゆちゃんのわすれもの 山岸文子
遅くなってゆく年賀状 永田順子
イソギクは化石のかわりに 古川克彌
イノコズチの虫こぶ 清水美重子
ヒマラヤスギの毬果 小野泰子
私たちのくらしと海藻 川本幸子
河童に会いに 松井恭
カラスビシャクを観察して 志田隆文
何もかも大きい~トチノキ~ 三輪礼二郎
キンラン・ギンラン 横山直江
早春の楽しみ 豊島秀麿
キンセンカ、ホンキンセンカ 佐藤久江
カラスウリの魅力 小林正明
イチョウ並木と精子 森江晃三
コスモスに秘められた物語 下田あや子
「蟻の火吹き」の語源について 志田隆文
新しい植物分類 豊島秀麿
サルスベリ(猿滑、百日紅) 宮本水文
小松原湿原への小さな旅 松村文子
野生植物の緑のカーテン 小林英成
江戸の文化を伝えるサクラソウ 黒子哲靖
工都日立のさくら物語 ―大島桜と染井吉野― 鯉渕仁子
ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属) 佐藤久江
能楽と植物 川本幸子
サカキの冬芽と花芽 古川克彌
ケンポナシみつけた 永田順子
セイダカアワダチソウの話 逸見愉偉
ヒガンバナ、そしてふるさと 森江晃三
いにしえの薬草‘ガガイモ’ 服部早苗
トリカブトの話し 三輪礼二郎
ツユクサ、花で染めても色落ちしてしまう欠点を逆利用!柴田規夫
アサギマダラ 横山直江
「思い込み」の桜 田中由紀子
常磐の木 タチバナ 清水美重子
柿とくらし 三島好信
植物に親しむ 小林正明






















