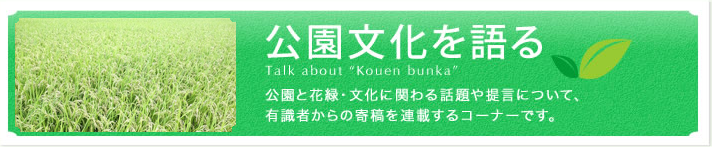
「公園文化を語る」は、様々な分野のエキスパートの方々から、公園文化について自由に語っていただくコーナーです。
第8回目は、全国の造園業者が集う、日本最大の造園緑化団体として、技術技能の向上、よりよい緑の環境づくりをめざし様々な活動を展開している(一社)日本造園組合連合会の井上花子理事・事務局長にご寄稿いただきました。

「リガーデン」ご存知ですか。住宅のリフォームに対抗して、1997年、講談社から刊行した園芸書『庭師が教える新しいガーデニング』の中で、私が名づけた造語です。当時はガーデニングブーム真っ盛りでしたが、庭中に草花の鉢があふれ、足の踏み場もない状態の庭を庭師が手を入れて、景色を作り、庭を再生した事例を2例掲載したときに「リガーデン」と名づけました。2016年では、ヤフーの検索でも1300万件ヒットするように知られてきたように思います。
そもそも庭園の世界では、「模様替え」といわれ、庭好きなお客さんは10年に1度ぐらいの間隔で、庭の改造を行ったものでした。庭に植えられた樹木は日の当たる方向に生長し、バランスが崩れてきます。植木の向きを替え、時には鋸を使っての荒透かしをするというような模様替えは良く行われたものでした。植木職人の手間が安い時代、暇なときに植木屋さんに仕事の場を提供するという一面もあったようです。
さて現代のリガーデンは、庭のある暮らしを楽しむ、家族構成の変化、ライフスタイルの変化などに対応して庭園を作り変える積極的なガーデンリフォームを行っております。
リガーデンのきっかけとしては、家族構成の変化、ガーデンに対する好みの変化があげられます。高齢のご両親と同居することから通路のバリアフリー化を契機としてリガーデン、逆に小さなお子さんが同居することで、石組みや池などを安全なものに変えるリガーデン、バラを楽しみたい、家庭菜園で収穫を楽しみたいという庭に対するニーズからリガーデンすることも多いです。
さらに庭園の管理費をコストダウンするために、リガーデンする方も増えてきました。(一社)日本造園組合連合会では一般市民を対象とした庭に対するアンケート調査を3年おきに実施していますが、毎回のアンケートに出てくるのは、庭にかける管理費のコストダウンの要望です。樹木や芝生の管理費用を少なくしたい、草取りが負担という方も大変多いです。ローメンテナンスの庭園・緑地つくりは公共の施設だけではなく、個人の住宅庭園でも大きな課題となっています。管理費を低減する庭へのリガーデン、高木を減らす、ご自分で管理できる剪定のしやすい樹木に変える、裸地を減らして、土系舗装や防草シートの提案などが考えられます。
一方で車が1台増えるので、庭園を壊して駐車場にしたいという造園人にとっても悲しいお話も多い。このようなときに無機質な駐車場ではなく、車と共存したパークキングガーデンとして、駐車場の舗装に石材を使い、駐車に邪魔にならないところへ植栽する積極的なリガーデンを提案しています。
リガーデンには高度な技術が必要で、専門業者としてのスキルが求められます。
①リガーデンを依頼される方は既存の樹木や石材を極力活用して、新しい庭園に変えてほしいという希望を持っています。材料を新しくすれば簡単ですが、それぞれ樹木や石材などに思い入れのあるものもあり、デザイン的に高度な技術が必要になります、もったいないというお客さんの思いをどう活かしていくかテレビのビフォーアフターではありませんが、高度なデザインテクニックが必要です。
②既存樹の移植がリガーデンにはつき物で、機械も入らない場所での移植が多く、長年の熟練の技能が活躍します。
③リガーデンの施工では、大型機械が入らない現場も多く、三又やそりで石を動かす伝統技能、担ぐといった人力施工が必要になることがあります。新規庭園よりも高度な技術技能が必要です。
本格的に庭を直すとなると、費用もかかるという方にはプチリガーデンをお勧めします。
管理費のコストダウンも考えて、庭の中に小道(パス)を作りましょう。草花や宿根草が庭
のあちこちに咲いている自然風の庭もとても雰囲気があっていいのですが、管理が行き届かないと、雑草が増えて、病害虫もやってきます。平板な石を敷くだけの簡単なパスを作り、草花や樹木を毎朝見回りするだけで、管理費もコストダウンできます。
花壇の縁取りをレンガから自然石の低い石積みに変えると和風モダンに、庭に重みが出てきます。
小さなお庭では、生垣に数種類の樹木を混色する混ぜ垣はいかがでしょうか。花が咲くもの、紅葉の美しいものを混植した混ぜ垣はそれだけで小さな庭園になります。
混ぜ垣・敷石・石積みも昔から日本庭園の世界で行われてきたこと、それらにもう一度スポットライトを照らして、庭のある楽しい暮らしになるようプチリガーデンから始めてみませんか。
※文中に出てくる所属、肩書等は、ご寄稿いただいた時点のものです。2016年12月掲載

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理
33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎




























