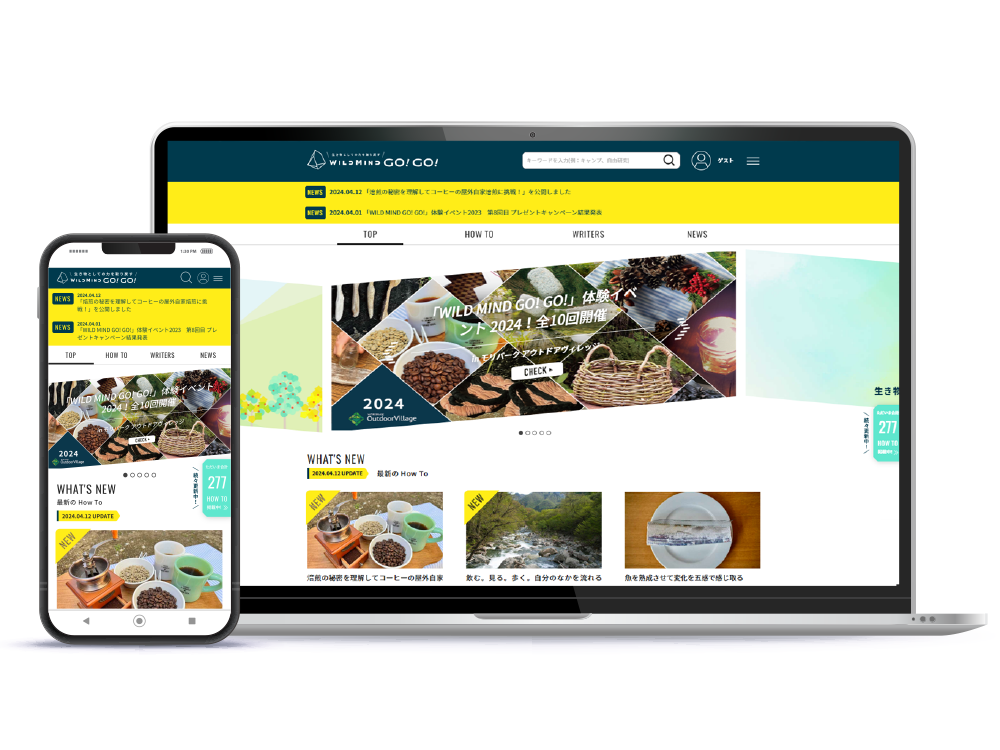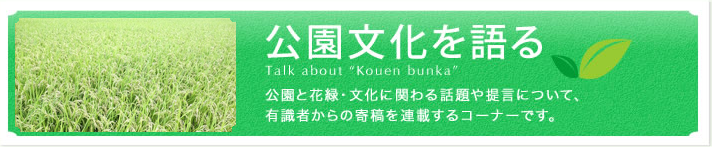
第29回は、カシオ計算機株式会社 事業イノベーションセンター SW技術開発部 部長で、カシオ、NEC、日立の社風を知るなど、開発、企画、社内改革、新規事業開発と幅広い経験を持つ谷治良高氏にご寄稿いただきました。谷治氏は、自然体験紹介サイト 「WILD MIND GO! GO!」 を主宰し、武蔵村山市 観光まちづくり協会の理事を務め、人と自然の共生や自然体験を通した人材育成など、幅広く活躍されています。

自然体験紹介サイト 「WILD MIND GO! GO!」
主宰 谷治 良高氏
私は2014年にカシオの携帯電話事業撤退の際に痛感しました。世界は「言われたものを作ればよい、言われたことをやれば良い」という時代から、「何を創るべきか自ら決めて挑戦する」という時代へ変わったことを。当時我々はその変化に対応できていなかった。
これからのVUCA※1の時代を生き抜くためには創造力、挑戦する力、くじけない力が必要という考えに至りました。
また、ちょうどその頃、昔に比べると自然が猛威を振るうことが増えているなと、気になっていました。“Feel the Earth”をコンセプトにした「G’zOne」という携帯電話の商品開発に携わっていたこともあり、自然や環境には関心があったのですが、暑さで人が亡くなるとか、大型の台風の数が増え、被害が拡大しているとか、そのようなニュースを目にすることが増えていたのです。3人目の子どもが生まれたばかりのタイミングだったことも影響してか、これからの未来においては「自然との共生」というテーマが大きな意味をもつのではないかと考えるようになりました。
一方カシオ計算機は「G-SHOCK」、「PRO TREK」といったアウトドアで愛用される商品をもっていました。
創造力、挑戦する力、くじけない力、自然との共生感を楽しく育み、カシオのアセットを活かすためには、自然体験を提供することが最適であると考えました。
「WILD MIND GO! GO!」は、“生き物としての力を取り戻すための自然体験を集めた体験メディア”です。
快適で便利な都市生活は、人が生き物であることを忘れさせるほどに、自然から遠ざかり発展してきました。WILD MIND GO! GO!の自然体験は人もまた「生き物」であることを思い起こし、「生き物としての力」と考えられる、感じる力、自然とのつながり、自然のなかで生きる技を取り戻せるようにデザインしています。
アウトドアのエキスパートだけでなく、アーティスト、科学者など、さまざまなスペシャリストがオリジナルの自然体験を紹介してくれており、大人も子どもも、サイトを見ながら自分でやってみることで、身近な自然に触れられるようになっています。
WILD MIND GO! GO!は「Feel the earth, Evolve yourself」~自然体験を通して、これからの時代に必要な、創造力、挑戦する力、くじけない力、自然との共生感を育む~という思いを持って活動しています。
自然体験というと、林間学校やキャンプなどで、遠くの雄大な自然の中で体験するもので、お金も手間もかかるものと、多くの方が認識していると思います。
WILD MIND GO! GO!は、週末に出かける公園や、家の近所を流れる川や空き地、路地、家の庭先、さらには家のなかでさえ「自然体験」はできるものと再定義します。
「子どもといっしょに空を見あげてみましょう。そこには夜明けや黄昏の美しさがあり、流れる雲、夜空にまたたく星があります。子どもといっしょに風の音をきくこともできます。それが森を吹き渡るごうごうという声であろうと、家のひさしや、アパートの角でヒューヒューという風のコーラスであろうと」センス・オブ・ワンダーの一説のとおりです。
このように再定義することで、自然体験が年一回の遠いものから、毎日の身近なものに変わります。そして野外教育でも重要とされている継続的な自然体験が可能となります。
自然離れが叫ばれて久しく、さらに多様性の時代、典型的な自然体験を提供することが最適解なのでしょうか。
悩んで出た答えが「自然体験は『料理』のようなもの」。料理には、日本料理、中華料理、イタリアン……などたくさんの種類がありますが、“好き嫌い“はあっても“良し悪し”はありません。自然体験もそれと同じです。自然体験をとにかく多く揃えてあげたら、子どもたちもどれかは「美味しい」と感じるはず。そして、子どもたちだけでなく、今は自然から離れている大人にとっても「美味しい」と思える自然体験がなにかしら提供できるのではないかと思い、そんな幅広い自然体験を提供するサービス、その時に出た言葉を借りると、「アウトドア版の“料理レシピサイト”」を目指すことにしました。レシピの講師はアウトドアのエキスパートだけでなく、アーティスト、デザイナー、科学者など、さまざまなスペシャリストが幅広いテーマで、他にはないオリジナルの自然体験を紹介しています。自然を深く探究した専門家の視点から眺める自然には、いままで見過ごしていた魅力や不思議との出会いにあふれています。
WILD MIND GO! GO!は料理におけるレシピサイトのように、それさえあれば先生がいなくても自分たちだけで自然体験ができる、そんなHOW TO形式のサイトにしました。今では270を超える自然体験のレシピが集まっています。
いつでも、どこでも、自分のペースで、自分の好きな自然体験ができる、それがWILD MIND GO! GO!です。
都市公園では遊具や施設に注目が集まりがちですが、実は計画的に自然環境を整えられていて、再定義され誰もができる自然体験、つまりWILD MIND GO! GO!の自然体験を実践するのに恰好の場所です。
多種多様な切り口の自然体験レシピからひとつ試してみてください。自然への解像度が高まり都市公園の緑の奥行が見えるようになります。すると別のレシピにも興味を持てるようになりますのでまた体験してください。さらに緑の世界が大きく深くなっていきます。都市公園は、遠くの大自然に負けない、「創造力、挑戦する力、やり抜く力そして自然との共生感を育む」ことが可能な場所なのです。
※1 volatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字から。変化が激しく複雑で、将来の予測が困難となった社会を表す語。
■関連ページ
WILD MIND GO! GO! : https://gogo.wildmind.jp/
カシオ計算機株式会社 : https://www.casio.com/jp/
公園文化WEB「公園の本棚」:生き物としての力を取り戻す50の自然体験 ―身近な野遊びから森で生きる方法までー:https://www.midori-hanabunka.jp/book?term=m8103
※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。(2024年5月掲載)

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理
33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎