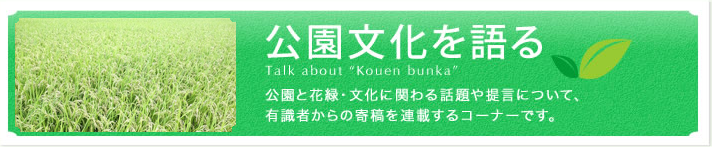
「公園文化を語る」は、様々な分野のエキスパートの方々から、公園文化について自由に語っていただくコーナーです。
第2回目 は、専門的な知識と技術を活用して地域の緑の普及啓発にも活躍している、一般社団法人 日本樹木医会 椎名豊勝会長に語っていただきました。

椎名豊勝 会長
国木田独歩は著書「武蔵野」で楢の雑木林に近代の新しい美しさを発見した。それから百年以上たった今、再び雑木林が脚光あび、社会的に存在することが求められている。
人里近くに存在する里山林は地域により独自の景観を形成する。そのうち雑木林はナラ類等が優占する林で、関東地方では武蔵野の特徴的郷土景観として、広く知られている。
しかし現在雑木林は危機に瀕している。もちろん燃料革命により薪炭が忘れさられ、雑木林自体の生産的意義は終了した。そして経済的価値を失った林は手を入れられない状況にある。
その結果、成長しすぎた雑木は風倒木となり、その後に外来植物が侵入し、放置された林床はアズマネザサ等で植生は単純化され、挙句の果てに粗大ゴミ置き場と化した雑木林が少なくない。
武蔵野の雑木林は人為的行為によって、植生遷移を止めたものである。すなわち萌芽更新・下草刈り・クズハキ・クズ伐り・萱刈り等の作業を祖先が営々と繰返すことにより、ナラ・クヌギ林として維持しつづけてきた。
雑木林は多く恵みを与えてくれる。往時、薪・炭等は燃料、灰は肥料、落葉は堆肥、緑葉は緑肥、落葉・刈下草を家畜・サツマイモの敷料・飼料・苗床材料、キノコ栽培のホダ木利用、萌芽更新後に発生したススキは屋根材、長期的に育成されたアカマツは梁材、春の山菜、秋のキノコ、季節的強風の防風・砂防林と生活のあらゆる局面で利用されてきた。
落葉樹林の季節的変化がもたらすきめ細かく多様な環境、落葉堆積による土壌豊穣化など生物多様性のバックボーンは、それを維持してきた先人達の雑木林育成努力によるところが大きいのである。
多種多様な生物生息環境を可能とすることのできる雑木林の環境特性が、今日的価値を得て大きくクローズアップされ、甦りつつある。すなわち、生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性に関し、雑木林の潜在能力は高く評価され大きな期待がかけられている。
近年多くの公園で雑木林の造成、保護が頻繁に行われている。昭和43年開園した皇居東御苑は昭和天皇ご発意により昭和60年に庭園一部を二の丸雑木林とした。国営昭和記念公園では、新たに6haの雑木林(こもれびの丘)を造成した。東京都は丘陵地公園として、数多くの丘陵部で雑木林を保護している。一方、平野部の雑木林は、それぞれの自治体により公園・緑地に、さらに民有地雑木林は特別緑地保全地区等で保全されている。そして多くの場合、公園雑木林管理にボランティア組織が積極的にかかわっている。
今や、雑木林は単に緑量として林を保護・保全するにとどまらない、むしろ雑木林の有り様が問われているのである。質として林床を含めた生態系としての健全度、植物・動物・菌類など種の多種・多様度、さらには種内の多様性(遺伝子の多様性)と生物多様性評価が公園雑木林の価値を決定する時代が到来するのも遠いことではない。
しかし、ここで問題なのは、従来経済採算の上に成立っていた雑木林の手入れを、今後誰がどのような形で担うのか、その行為を社会全体が、より高い評価与える構造を明確にする必要がある。
担うのは、ボランティアなどの公園市民力であろう。都市公園・緑地ならではの潜在的コミュニティー機能こそが公園市民力結集の源泉である。
さらに雑木林管理の公的評価システムが必要であろう。また、マスコミへの露出拡大等広く世論の支持を得る方策を進めるべきである。参加市民が社会的に明確な目標値をめざして努力することでき、評価が得られるという環境整備を行うことで、社会参画意識の向上、いきがい発見につながる。そして動植物の生物多様化が目に見える形で自己認識ができ、成果を各個人が獲得できる、この公園市民活動は大きな可能性を秘めている。
※文中に出てくる所属、肩書等は、ご寄稿いただいた時点のものです。2014年12月掲載

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理
33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎




























