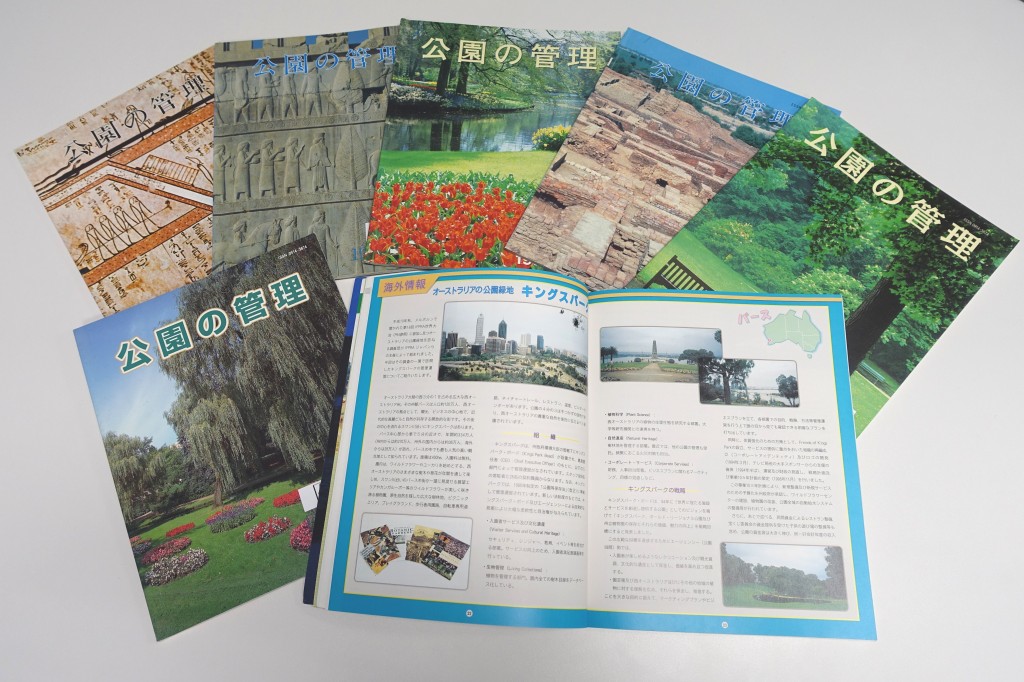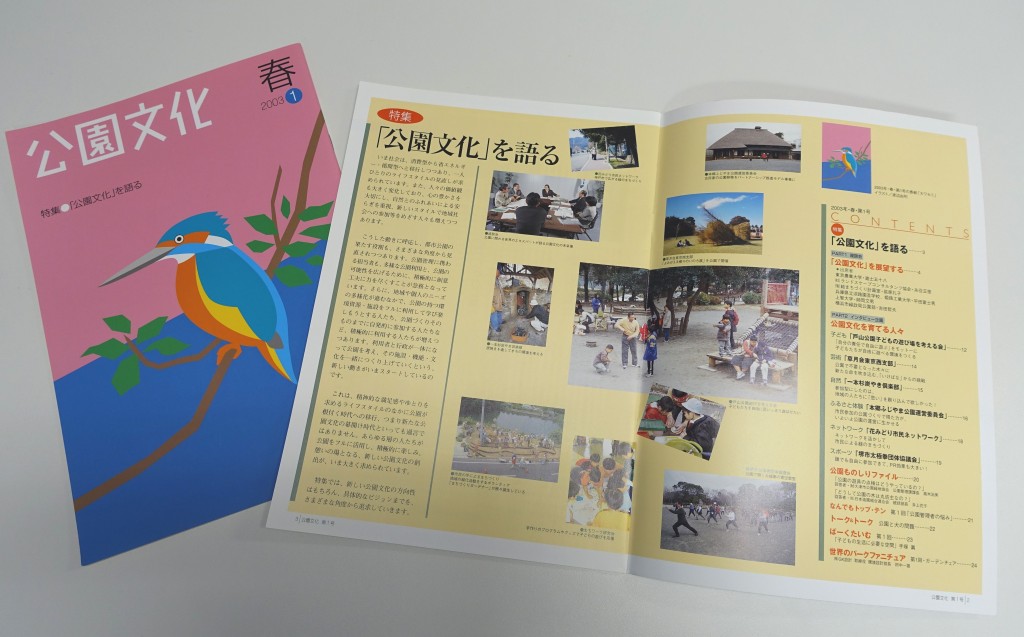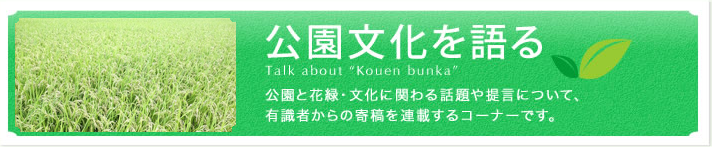
「公園文化を語る」は、様々な分野のエキスパートの方々から、公園文化について自由に語っていただくコーナーです。
第5回目は、公園文化WEBの前身であった一般財団法人 公園財団 機関誌『公園文化』の発刊に関わっていた
森本千尋さんに語っていただきました。

森本千尋さん
(キューバの世界遺産(文化遺産)(1998年登録)
「トリニダードとロス・インヘニオス渓谷」。
かつてのサトウキビ農園で奴隷たちを監視していたイスナーガの塔にて)
(財)公園緑地管理財団(当時)が、それまで機関誌として発刊していた『公園の管理』をとりやめ、『公園文化』の発刊を開始したのは、2003年です。
『公園の管理』は、公園管理の専門的機関として設立された財団として、全国の公園管理の質の向上を図るための情報発信の役割を果たすものとして、1986年から年1~2回発行していました。従来の維持管理主体の公園管理から公園利用をより豊かにしていくための公園管理を目指し、公園管理を担う地方公共団体向けに、いかに管理すべきかを専門家や実務者の方に述べてもらったり、こんな管理をしている公園がありますよという情報をお知らせしたり、というような編集内容でした。
主に行政担当者向けに公園緑地の計画、設計、整備に関する情報提供を担っていた(社)日本公園緑地協会発行の『公園緑地』との役割分担も意識していたものですが、「公園整備の時代から公園管理の時代へ」と言われるようになり、『公園緑地』も公園管理関連の話題が徐々に増えてくる中で、財団機関誌の方向転換が求められました。
方向転換のポイントは、読者層を行政担当者から公園を利用する人たちにすることでした。さらに、これは実現できませんでしたが、一般書店でも扱ってもらえるものにせよという要求もありました。
当時の議論についての資料は手元には残っていませんが、まず、読者層を広げるという方向で考えていく中で、『公園文化』が生まれました。
さて、機関誌の誌名をどうするか。
公園を日々の生活の中で当たり前のように使いこなすという意味を込めて「公園生活」という案も上がりました。また、カタカナの案としては、英語の「文化=culture」と同じ語源(ラテン語のcultus)を持つ「耕す=cultivate」をアレンジしたものや、一般の人に関心を持ってもらうためにおしゃれなイメージで公園を表す「パルク」(フランス語、スペイン語の公園の発音)などもありました。
『公園の管理』の編集委員長であった進士五十八東京農業大学長(当時)に機関誌の方向転換についての報告をした際、この誌名についても相談をし、「公園文化」を支持いただきました。もっと市民を巻き込む意味で「公園市民」という案も伺いました。当時財団事業として立ち上げようとしていた「公園管理運営士資格」とも結びつけ、市民対象の公園マネジメント資格を作って、公園市民の育成に関わってはどうかというお話もありました。
『公園文化』の企画検討段階でイメージしていたのは、公園での豊かな時間の過ごし方を知っている、またそれを実践している人がたくさんいるような公園像を作っていきたいということでした。禁止事項が多い、子供が遊ばない、老朽化していて利用する人を見かけない、人気(ひとけ)がないから危なそうなど、公園に対する負のイメージを持つ人の声も聞かれる中、こうすればもっと面白い公園になるよということを公園を利用している人から聞き出すことができたらよいのではないか、公園を管理する立場にある行政担当者だって公園の楽しい使い方がなんでもわかっているわけはない、いろいろな人が公園を使いこなす知恵を展開していくような誌面にしていきたい、というようなことを考えていた気がします。
発刊にあたって、『公園文化とは』を一言でいうと何だろうと考え、事典、辞書などを見ました。
広辞苑では「文化」の意味を「人間が学習によって社会から習得した生活の仕方の総称。衣食住をはじめ、技術,学問,芸術,道徳,宗教など物心両面にわたる生活形成の様式と内容を含む。」と言っています。この定義を借りるなら、公園文化は「人々が公園を利用しながら時間をかけて身に付けていった公園を使いこなす生活様式」ということになるかもしれません。ここでいう生活様式とは、公園がある地域に居住している人の現在の生活だけではなく、公園を取り巻く地域のこれまでに積み重ねられてきた歴史や様々な知恵なども生かしたものと考えます。そうすることで、公園が地域力の発現の場として大きな力を発揮していくことも可能でしょう。
財団事業に「公園夢プラン大賞」というものがありますが、これに応募されてきた方々は公園文化を築いている人たちなのかもしれません。
日本文化の代表的なものの一つに歌舞伎があります。松竹株式会社による歌舞伎の説明には幕府に禁止されながらも、「お上に頼らず、市井の人々が育ててきたところに大きな特徴があります。……どんな苦境も乗り越え、成長の糧にしてしまう――。興行主である座元(ざもと)や歌舞伎俳優、彼らを支えるスタッフに流れる反骨精神もまた、歌舞伎がこれまで受け継がれる上で欠かせないものでした。」とあります。(※)
公園も明治政府によって文明都市として備えられるべき施設とされ、その後も都市住民の健康、都市環境の改善、防災など様々な機能を有するものとして都市に不可欠の施設となっています。けれども、これまでは行政にお任せで、与えられたものをそのまま使うだけになりがちでした。公園文化は、公園を取り巻く人たちが地域力やアイデアを集め、一種の「反骨精神」でこれまでと違うものを追い求めていくことにより生まれるものかもしれません。
※歌舞伎公式総合サイト歌舞伎美人(かぶきびと) http://www.kabuki-bito.jp
※文中に出てくる所属、肩書等は、ご寄稿いただいた時点のものです。2015年12月掲載

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理
33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎