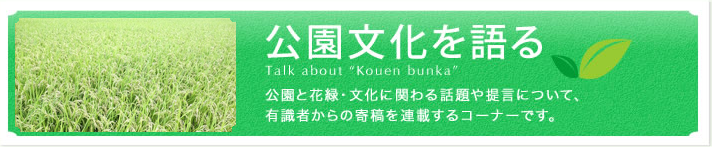
第25回は、今年5月に公益社団法人「日本植物園協会」の初の女性会長に就任した、水戸市植物公園長 西川綾子氏にご寄稿いただきました。西川氏は、昭和62年の水戸市植物公園開園以来、植物公園に携わる一方、長くTV番組で草花の解説を担当するなど、幅広くご活躍されています。また、2024年に水戸市で開催される「日本植物園協会」の第59回大会は、園長を務める水戸市植物公園が初めてホスト役となる予定です。

水戸市植物公園園長 西川綾子氏
植物園は、イタリアで医学校が研究に役立つ植物を集めて薬草園を作ったのが始まりといわれ、日本でも小石川植物園の御薬園からスタートしています。多くの植物を集め、それを維持するために栽培管埋を行い、医薬・農業・工業・商業などの産業で有用植物として利用するため多方面にわたって調査・研究が行われる学術的研究を行う施設であると同時に、植物を展示・公開し、植物や緑化などの啓発・普及を行う教育の場でもあります。
全国約120の植物園が加盟する(公社)日本植物園協会では、「絶滅危惧植物の保全事業」や、野生植物ばかりでなく日本で古来より培われてきだ伝統的な園芸植物を文化として捉え重要な遺伝資源として保全する「ナショナルコレクション事業」を柱に、人間にとって植物がいかに重要かを訴える普及活動などに取り組んでいます。
植物園は、設置目的で各園の目指すところが多種多様です。花や緑に親しみながら植物を学べる園芸面と、レクリエーション的な部分が強い施設が多くなり、来園者からは花畑のような群落の美を求める声を多く聞きますが、植物園は世界の植物の個々の魅力を伝える場〜意外とこの事に気づかない方が多いように感じます。
そんな植物園に私が勤務して35年以上が経ちます。東京の下町で育ち、幼い頃から花が大好きで近所のお宅で咲くニオイバンマツリ、ハナニラ、タイザンボク、ジンチョウゲなどの花を見つけては、小中学校の帰りに立ち寄ったものです。近所には、桜で有名な飛鳥山公園やバラやツツジが咲く旧古河庭園もあって、名園というよりも四季の花や緑、池や石が楽しめる身近な遊び場でしたし、土曜の午後は枝垂れ桜が咲く六義園を友人たちと訪れた事も忘れられない楽しい思い出です。
幼稚園の時、初めて見つけたヤブガラシの小さな花はオレンジとピンクで当時売っていたアイスキャンディーを連想させ嬉しい発見でしたし、ヘクソカズラの葉を触った時の悪臭の記憶はいまだに鮮明な思い出です。
自分のような植物が大好きな少女を増やすポイントは、幼い頃に庭園や下町で出会った花たちに感動した、植物との思い出があることではないでしょうか。
ところで来年前期のNHK連続テレビ小説が「日本の植物学の父」と言われる牧野富太郎先生をモデルにした「らんまん」に決定しました。子供の頃から好きだった植物のため、夢のため一途に情熱的に突き進んでいく波乱万丈な先生の生涯です。様々な植物やエピソードが紹介されるでしょう。ドラマの牧野先生を見た子どもたちが「植物園に行ってみたい。植物ってこんなに面白かったんだ」と感じてくれるのではないかと期待しています。
私が小学生の時、国語の教科書で牧野先生のエピソードを読み「植物が好きだと研究者になれるんだ」と憧れた思いは今も変わりません。
来年は、朝から植物や植物園が紹介され植物の魅力を伝えるチャンス!全国の植物園に呼びかけ、牧野先生にあやかって植物の魅力を伝えていきたく思います。
植物園を未来につなげていくためには、牧野先生のような植物研究者や技術者が必要です。「大人になったら植物園に勤めたい!」そんな子どもたちを増やすには、植物の魅力に気がつき、好きになってもらうことです。
職場である水戸市植物公園では、子どもたちが園内を駆け回りながら遊び感覚で植物に親しめるように、「バナナは木か草か?」「野生のバナナに種はあるか?ないか?」のようなクイズを年間で作成をしています。親子で楽しみながら植物を学ぶ工夫をしたおかげでクイズを楽しみに来園する家族連れが増えました。幼い頃の思い出が一生の思い出になりますようにと願いながら、クイズにチャレンジする姿を見守っています。

また県内の大学で、小学校や幼稚園の先生を目指す学生にハーブをテーマに授業を行っています。座学で理論と歴史に触れますが、メインは実習。種をまいて苗を作りハーブガーデンを作って収穫・利用するという理科の実習です。最初は植物に興味がない学生が多かったのが実習を続けていくと興味を持ち始め、バジルやハトムギなどを自宅に持ち帰って栽培する学生も増えました。
「みんなが教師になったら植物の面白さを子どもたちに伝え植物園に遠足に来てね!」と言いながら授業を続行中ですが私の壮大な計画は未来で実現するでしょうか。
植物園の魅力を未来につなげていくために、できることから始めています。
作成中-1-1024x768.jpeg)
■関連ページ
水戸市植物公園:https://www.mito-botanical-park.com/
公益社団法人日本植物園協会:http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/
※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。(2022年12月掲載)

33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎


























