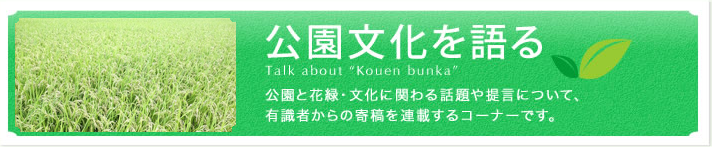
第22回は、和菓子屋・虎屋にある菓子資料室「虎屋文庫」の河上 可央理さんからご寄稿いただきました。虎屋文庫は、菓子の見本帳や古文書、古器物などを保存・整理するとともに、様々な菓子資料を収集し、機関誌『和菓子』の発行、展示開催やホームページでの連載「歴史上の人物と和菓子」などを通して、和菓子情報を発信しています。

左上から右回りに、羊羹製『手折桜 』、きんとん製『向日葵』、 薯蕷製『山路の菊 』、湿粉 製『雪紅梅』
公園を訪れる楽しみの一つに、植物や自然の風物の観賞がありますが、これは和菓子にも共通するところがあると思います。
和菓子、なかでも、いわゆる上生菓子には、植物をモチーフとしたものが数多くあります。和菓子屋によく足を運ぶ方は、桜の菓子一色の店頭を見て、花見の季節に心が浮き立ったり、紅葉の意匠(デザイン)から、秋の山に思いを馳せたり、和菓子によって季節の移り変わりを感じた経験もあるのではないでしょうか。
和菓子の意匠に植物を取り入れる文化は、少なくとも300年は遡ることができます。

写真左より、花いかた(花筏)、しら藤(白藤)、水山ふき(水山吹)、 たつた餅(龍田餅)、小しきし(小色紙)
こちらは虎屋の元禄8年(1695)の菓子見本帳(菓子のデザイン帳)で、現在の商品カタログのように使われたものです。花筏は、散った桜の花びらが川を流れていく様子を筏に見立てた言葉。白藤は、銘の通り白い藤の花をイメージしたもの。水山吹は川辺に山吹の花が咲き乱れる情景を思わせます。龍田餅は少し不思議なデザインですが、紅葉の名所として有名な奈良の龍田川を想起させる銘です。周りを縁取る小豆の粒は、紅葉の葉を表したものでしょう。
これら桜、藤、山吹、紅葉などはいずれも、古くから和歌に詠まれ、美術工芸品の題材にもされてきました。長い歴史の中で日本人が育んできた美意識が、和菓子にも取り入れられていることがわかります。

薯蕷製『水山吹』 と川辺に咲くヤマブキ 薯蕷製は、上用粉(うるち米の粉)につくね芋 (山芋) をすってもみ合わせた生地で餡を包んで蒸したもの。
現代に話を戻しまして、とらやを例に、いくつか冬の菓子を見てみましょう。たとえば、『氷の上』という、水仙をかたどった菓子があります。菓銘からは、寒い冬、凍りついた湖や池のほとりに咲く水仙の花が想像されます。

羊羹製(餡に小麦粉・寒梅粉を混ぜて蒸し、揉み込んだもの)の生地で、木型を使って作られる『氷の上』
『新山茶花』のように、植物が抽象的に表現されたものもあります。紅と白というシンプルな2色の色合いですが、不思議と山茶花の凛とした美しさが感じられるようです。

紅白に染め分けた外郎で黄色の餡を包んでいる。 切ると中餡の黄色が見え、
おしべを思わせる。
また、1月になると、早くも梅の菓子が店頭に並び始めます。梅は他の花よりも早く咲くことから百花の魁(さきがけ)と呼ばれ、春を告げる花とされます。実際にはまだ寒い季節に販売されることも多いのですが、梅の菓子の登場によって、冬から春へ季節が移りつつあることが感じられます。

羊羹製『寒紅梅』、きんとん製『木の花』、薯蕷製『月ヶ瀬』
きんとん製は、そぼろ状にした餡を、煉切や求肥で餡玉を包んだ芯のまわりにつけたもの。
面白いのは、同じ梅モチーフの菓子でも、意匠や菓銘がさまざまなことです。『寒紅梅』は寒さの中に咲く一輪の紅梅。『木の花』という銘は、『古今和歌集』の序に「なにはづ(難波津)に咲くやこの花冬ごもり……」とあるように梅の別名であり、紅白のそぼろは、咲き誇る梅を連想させます。『月ヶ瀬』は奈良の地名で、名張川の渓谷沿いにある梅の名勝地。白い饅頭に青い線が入ったシンプルな意匠ですが、菓銘とあわせて見ることで、川の両岸に白梅が咲き匂う情景が浮かぶ趣ある菓子です。
『寒紅梅』は花の形、『木の花』は赤と白という色合いの妙、『月ヶ瀬』は、梅が咲き匂う情景など、それぞれ違った視点で梅の美しさを捉えており、植物を観賞する際の視点を教えてくれるようでもあります。
四季折々、植物によって公園の景色が異なる表情を見せるように、和菓子も、春は早蕨、桜、菜の花、山吹、夏はつつじ、菖蒲、紫陽花、朝顔、秋は撫子、萩、桔梗、菊……等々、季節ごとに違った華やぎを見せます。和菓子屋の店頭を眺めるだけでも和みますが、好みのものを買って帰り、自宅で和菓子の花見をしたり、和菓子の写生帳を作ったりして、楽しんでみてはいかがでしょうか。
◆関連ページ: 菓子資料室 虎屋文庫:https://www.toraya-group.co.jp/toraya/bunko/L
※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。(2021年12月掲載)

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理
33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎























