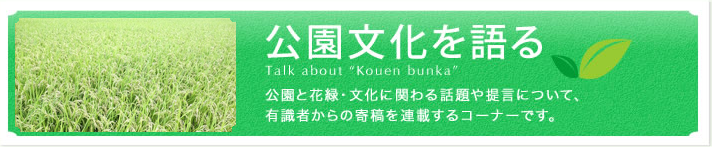
~瀬戸内“因島”における自然系博物館連携の試み~
第12回は、大分マリーンパレスやマリンワールド海の中道の水族館にて海洋生物の普及啓発に努め、『魚のつぶやき』『海のふしぎカルタ読本』『居酒屋の魚類学』他多数の著書によって魚や海の面白さを発信されている福山大学生命工学部海洋生物科学科 内海生物資源研究所 教授 高田 浩二氏にご寄稿いただきました。

福山大学生命工学部海洋生物科学科
教授 高田 浩二氏
この春、大捕り物で世間を騒がせた「しまなみ海道」につながる1つの島である「因島(いんのしま)」が、私の現在の勤務地「福山大学内海生物資源研究所」である。小島と言っても、広さは35㎢、外周は32㎞もある。写真1は研究所に最も近い大浜港から因島大橋方向を撮ったものだが、橋の左側に見える小さく白い建物が研究所で1989(平成元)年に、大学の創設者である宮地茂の出身地の大浜町に誕生している。また敷地内には小規模な大学附属水族館「マリンバイオセンター」があり(写真2)、大小約30個の水槽には瀬戸内の沿岸魚類を中心に増養殖に関する水産生物なども展示されている(写真3)。
 写真3 藻場、砂場、岩礁域などの生息環境を再現する水槽
写真3 藻場、砂場、岩礁域などの生息環境を再現する水槽島内には現在およそ2万5千人が住み、かつては因島市としての行政区であったものが、平成の大合併で尾道市に併合されている。島民は主に海岸沿いの数十か所ある集落に住んでおり、大学研究所は北東部の大浜町にある。また後述する植物園のある重井町は北部に位置し、両者の間は車で5分ほどの至近距離である。また重井町内にも小さな漁港(写真4)があり、釣りや網などによる漁業で生計を立てている住民もいる。
 写真4 重井町内の漁港と係留漁船
写真4 重井町内の漁港と係留漁船
重井町は、明治中期に我が国に導入された除虫菊の生産地の拠点1つとして栄えた地域で、1955(昭和30)年頃まで蚊取り線香の原材料を供給するために栽培が続いていた。今は、鑑賞や観光を目的に一部の地域で植えられており、5月初旬に、重井港を見下ろす丘の上や同町内の植物園(因島フラワーセンター)周辺において、見事な花畑で楽しむことができる。またこの集落には、除虫菊で繁栄していた当時を偲ばせる立派な蔵造りの民家も多数残っている(写真5)。
除虫菊の商業的な生産が終えた今の地域での農産物は、瀬戸内の温暖な気候を利用して、花卉や柑橘類をはじめ、ビニールハウスなどでのフルーツ、野菜類の栽培が中心に農業が営まれ、半農半漁で暮らしている住民もいる。写真6は、その耕作地の遠景の丘の上に建つ因島フラワーセンターと呼ばれる植物園で、ここでの花卉栽培と管理に地元の農業経験者等が従事している。
1989年(平成元年)に広島県は、因島地域の振興策の一つとして“海と島の博覧会”を開催し、会場として使われた植物園を翌年に広島県立因島フラワーセンターとしてオープンしている(写真7)。本島は造船の町であったが、因島市(当時)は新たな町興しの施策として「水軍と花とフルーツの島」を掲げて本施設を整備し、その後、管理は因島市と合併した尾道市が引き継いでいる。このため、島内には村上水軍城に代表される関連遺跡群、さらに花とフルーツでは、因島フラワーセンターを中心にした四季折々の花卉の鑑賞、レモンや八朔などの柑橘類の栽培、関連加工食品の製造販売などが島の観光資源になっている。
ところで、国内に数多くある島々の中で、水族館と植物園がほぼ同時期に整備されて今もなお公開されている地域は稀有である。紹介してきたように、水族館では瀬戸内海の海洋や水産生物を展示し、沿岸水域の環境に関する情報発信をしている。一方で植物園は、除虫菊や柑橘植物などに代表されるように、瀬戸内の温暖な気候に育まれた植物が育成展示されている。となれば、この両者が連携した博物館活動が展開されれば、教育面や観光面でも大きな成果をあげる可能性を秘めている。しかし、これまで両者は、組織や運営が異なることもあって、一緒に手を携えての活動がなされてこなかった。なんともったいないことか。
そこで筆者は、2018(平成30)年度に、地元の重井小学校の5年生を対象に、子どもたちが、両施設の見学や専門員から講話指導を受けるだけでなく、地元の自然と深く関わった仕事をしている漁業や農業従事者にも出会い、多くの人々とのコミュニケーションを通して、瀬戸内海や因島の野山や沿岸域の環境がお互いに有機的につながり、人々の手によって守り育てられていることに気づくことを狙った学習を展開している。
重井小学校の5年生は、この島の特産品であった除虫菊を4年次に調べ学習に取り組み、5月初旬に、因島フラワーセンターで開催された除虫菊祭りに合わせて、会場に集まった市民へ学習成果の発表会を行い、あわせて植物園の温室内でのタブレットを使った植物の観察記録の学習を行った(写真8)。
さらにその後、福山大学マリンバイオセンター水族館の教員が小学校に出張講話し、瀬戸内海の環境の特性や地域の水産生物と水族館での飼育展示について事前レクチャーし、水族館で調べてみたいテーマを各自で決めた。さらに後日、福山大学マリンバイオセンター水族館の見学学習を行い、同様にタブレットを使って観察記録した(写真9)。
これらの一連の活動により、子どもたちは、普段の食生活や釣りなどで見かける水産物の意外な能力や暮らしぶりに驚き、新たな発見からさらに調べ学習へと発展させている。その後の島の漁業者(漁師)との交流学習では、単に瀬戸内の漁業にだけでなく、魚のオスメスの見分け方、夜行性の魚について尋ねるなど、水族館で学んだことが地域学習に活かされている。さらに、メロンなどのフルーツ栽培をしている農業従事者との交流学習では、温暖な瀬戸内の気候と植物の栽培が深い関係にあることに気づくなど、本プログラムに関与した地域の人々すべてが、地元の自然や産物の素晴らしさを再認識し、積極的に発信交流できることを目指している。今後も、地域にある産業や歴史などすべてが教育資源に活用できるという視点で見直し、そこに大学や水族館が核となってICTも導入しながら「地域学習コーディネーター」となれるように働きかけていきたい。
文末になるが、筆者は1988(昭和63)年から2014(平成26)年の間、福岡市にある国営海の中道海浜公園にある海の中道海洋生態科学館(マリンワールド海の中道)に勤務していた。振り返ればこの地も、四方を海に囲まれた半島構造の、花と緑に溢れる広大な公園の中で、水族館の運営管理に携わってきた。その当時からも、共に自然の恩恵を享受する公園事業者として、人々の生涯学習に協働で寄与するという連携意識をもち、数多くの自然学習のプログラム実践を行っていた。つまり、ここでの経験が、今いる因島での活動に大きなヒントと後押しを与えてくれていることは間違いない。過去に支援応援していただいた人々に感謝する毎日である。
※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。2018年8月掲載

33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎






























