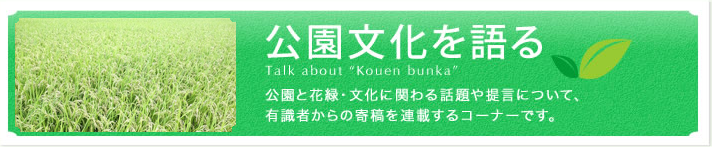
「公園文化を語る」は、様々な分野のエキスパートの方々から、公園文化について自由に語っていただくコーナーです。
第1回目 は、公園のプランニング・デザイン・マネジメントについて、都市農村計画や環境計画の視点から、かつ国際的な視野も含めて発言している、一般財団法人 公園財団の蓑茂壽太郎理事長に語っていただきます。
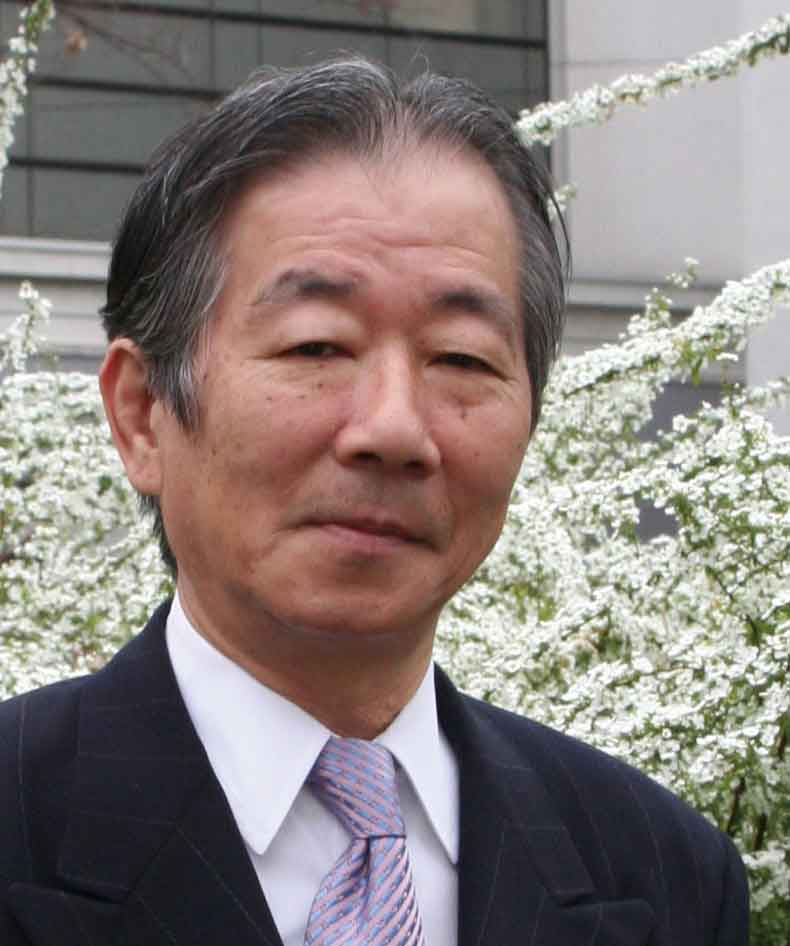
一般財団法人 公園財団
蓑茂壽太郎 理事長
公園を文化的な視点で捉えると、大きく二つに分けられます。一つ目は、公園が文化の発祥に関係しているということ。たとえば、日本を代表する都市公園である日比谷公園は、園芸、音楽、そして洋食など西洋の文化を取り入れた舞台として知られています。
二つ目は、公園は地域文化を高め、さらにこれが地域の活力に繋がるということです。文化の語源は「カルティベート(耕す)」といって、その空間での活動、すなわち“振る舞い”が文化になることを表しています。私の公園での経験として、かつて、国営昭和記念公園に「ニュースポーツ施設」が整備され、現地を訪れた時のことが思い出されます。ローンボウルズやクロッケーのプレイヤーが、真っ白な上下の正装で競技している光景を見て、大きなカルチャーショックを受けました。それは単なるスポーツとしてではなく、公園での“振る舞い”を通して、まさに新しい文化が導入されようとしている風景でした。このような「振る舞いの風景」の大切さは、公園で展開されている園芸にも当てはまります。コスモスなどの花畑やバラ園などの花壇、雪割草などの山野草は「園芸文化」として来園者を楽しませてくれますが、これからは更に「公園文化」へと昇華させる手法が大切になるでしょう。
一方で、公園で展開されるジャンルではなく「地域」での文化という捉え方があります。国やその地域によってさまざまな個性豊かな文化があり、公園という“空間文化”とこの“地域の文化”を融合させた考え方が重要だと思っています。
公園財団では、「地域生まれの世界水準」を合言葉に公園マネジメントを実践していますが、この根底にあるのは公園文化です。イベントや普段の公園の使い方を公園文化まで進化させるなら、公園の価値向上は進むと思っています。またそうすることで、公園利用者の多くが味方についてくれるものと信じています。
公園ならではの固有の文化があるはずです。そこで、公園で見られる「ならではの振る舞い」とは何かを考えてみます。人が自然と接した時の振る舞い、草花と接した時の振る舞い、動物と接した時の振る舞いなど、どのようなものがあるでしょうか。
最近、ドイツの公園で経験した事例ですが、森の中の園路の脇に小路が作られていて、そこにはちょっとした遊具が設置されていました。子供はその小路の遊具で遊びながら先に進み、親は子供を見守りつつ並行して散策を楽しむ仕掛けになっています。子供は林間の散歩に飽きないし、親は安心して景観を楽しめるというデザインです。同じ空間にいながら、親と子供がそれぞれの時間を楽しめ、融和できるところがいいですね。このように人が森と接する仕掛けを工夫することで、新しい振る舞いが生まれます。それが公園文化につながるのだと思います。
人が自然と接する行動面の振る舞いが、どのようなものを生み出しているのかに関心を持ってみるのも一つです。音楽や俳句、絵画、環境芸術として現れることもあるでしょう。そこまでを関心もって見てみると、人の“振る舞い”から公園文化を次々とイメージすることができます。
これからの公園は、機能を掲げるだけでなく、公園の使命を如何に達成するかが重要な時代だと思います。人々の公園への期待が機能から使命に変わるという見方です。従来、公園づくりはレクリエーション機能、防災機能、景観構成、あるいは環境保全機能をもつものとしてなされてきましたが、最近は、現存する公園がいかなるミッションを持っているか、果たしているかの関心に移っています。私の認識では、機能から使命への変化は、文化への志向の高まりといえます。
これまでの日本は経済大国づくりにまい進してきました。経済成長から高度経済成長へとひたすらこの方向に駒を進めてきましたが、過去の時代の繰り返しを見てみると、新しい文化というものは、混乱期や経済隆盛期を経て、その次に起こる一つのサイクルの中で生み出されているように感じられます。混乱期の後にそれを取り戻す経済の時代があり、経済的余裕の中で文化が芽生えるという流れが見て取れます。
ブリヂストンの創業者・石橋正二郎氏を例にあげてみましょう。かつて福岡県久留米市の緑のまちづくりに関与した時に、ブリジストン通りとして市民に親しまれているケヤキ並木の存在を知りました。ブリヂストンの創業者・石橋正二郎氏の発案のようです。氏の生家は、足袋(たび)やはんてんなどを作る仕立屋でした。家業を継いだ石橋は、仕事の効率を上げるために足袋専業に経営転換し生産効率を上げるのに成功しました。石橋氏が次に行ったのはモニター調査です。足袋を最も買いに来るのがお百姓さんだという結果を得て、水に強い丈夫な足袋を作ることを考えました。今でいう消費者目線での商品開発というわけです。その結果、生まれたのが裏にゴムを縫い付けた地下足袋でした。ゴム付は値段が高く、農家には容易に手が届かなかったのですが、ちょうど関東大震災が発生し、地下足袋は震災復興の作業をする人たちの履物として大ブレイクしました。
石橋は地下足袋の次に何を商品とするかを考えるため、ヨーロッパ視察に出かけました。そして日本がまだ馬車中心の時代にヨーロッパでは車が主流になってきているのを見て、地下足袋の次はタイヤだと思い、タイヤの研究開発そして生産をはじめたようです。詳しくは述べませんが、その後、石橋文化ホールや美術館など様々な文化活動を通じた社会貢献をしていることを見ると、混乱や経済と比較して並べてみる文化の特性が見えるように思います。
どうでしょう。皆さんは文化という言葉を耳にして、あるいは文字を見て、従来は「伝える文化」が主流と感じているのではないでしょうか。これに対して、公園財団の前身である公園緑地管理財団時代の機関誌『公園文化』では「育む文化」を強調していました。もちろん、この二つの文化、伝える文化と育む文化を目指す意気込みは現在も変わりません。これに加えて、今後は「生み出す文化」に挑戦することが大切なのではないでしょうか。
2020年東京五輪の主会場となる国立競技場設計者のザハ・ハディド氏の最新作である、ソウル市の「東大門デザインプラザ」がこの3月にオープンしましたが、建築史の中川理さん(京都工芸繊維大学教授)は、既存のものとの調和だけではなく、都市デザインとの連動の重要性を訴え、デザインという力をもって、新しいものを生み出す。と語っています。(2014.3.27「読売新聞」記事から)
私は、このデザインにおける新しいものを生み出すという積極性に共感します。そこで、私たちは「伝える」「育む」「生み出す」という3つの文化で、これから「公園文化」を考えていくべきではないかと思います。
2004年に景観法が制定されて10年が経過しました。景観法が運用されるようになって、従来の文化財行政のみによる取組から、これとは違った新しい動きが起きてきているように感じます。育成概念や創造が始まったということです。これからは、新しく地域文化をつくっていくことが本格化するのではないでしょうか。
実は、この3月にドイツのハイデルベルクに行く機会がありました。そこで体験したのが、ドイツのIBA(International Bauausstellung)(国際建設展覧会)の活動です。これは100年の歴史があるもので、ハイデルベルクを舞台に「ナレッジベース」(知識基盤型)を基本とするまちづくりを議論しようというシンポジウムが今回でした。これが実は文化に近いもので、公園でも「ナレッジベース・パーク」という考え方があると感じました。そしてまた、日本の都市緑化フェアーが曲がり角にきているように見えるのは、この「ナレッジベース」が見えていないからではないかと思ったわけです。文化を大事にしないと、やっていることに深みが感じられないものです。
私は、食は公園文化につながりやすいと思っています。なぜなら食には様々な振る舞いが付いてくるからです。
私たちがマネジメントしている公園に国営アルプスあづみの公園があります。そのそばの穂高に別荘を持つ友人がいて、このご夫婦はそば打ちをし、山でキノコを採るなど、自然と調和したライフスタイルを楽しんでいます。私はその人に、「森にピザ窯を作ってはどうか」と提案しました。ピザ窯は、国営公園にも本格的なものが設置されているのをその友人は知っています。しかし、そのピザ釜は個人もしくは小グループでは使い勝手が悪く、年に数回しか使用されていないのではないかと言っていました。
公園で食文化を楽しむのであるなら、高度に施設化されたピザ窯を利用するのではなく、来園者に、段ボールの型枠づくりから始めてもらって、土・消石灰・セメントと刻んだ麦わらを捏ねて土団子を作ってのピザ窯作りを体験してもらった方がよいと思います。ここに森の中での一つの振る舞いが登場してクラフト文化がはじまります。そしてしばらく日にちをおいて次の来園時に森の中で手作りのピザ焼きを楽しむなら、もう一つの振る舞い、つまり食文化が登場するのです。このピザが評判となり、東京から友達を連れた人がたくさん来る。公園文化のためには、施設だけでなくそうした気の利いた設備をこしらえるプロセスが必要なのかもしれません。設備が作れると、そこに新しい振る舞いが起きると期待するのはどうでしょう。
公園の計画ではactivity(活動)を一生懸命想定します。実はその活動とは、人の“振る舞い”なのです。園芸文化も、スポーツ文化ももともとは一人一人の活動に他なりません。人が公園でどういう振る舞っているのか、そこを考えると大変面白いことがわかります。
雨や雪が降ったら公園の利用者はガタンと減るのが普通です。ですが、雨や雪が降ったからこそ、晴天の日では見られない人の振る舞いが起きるはずです。たとえば、雨が降ると公園内に水溜まりができます。その水溜まりに真っ赤なペンキを流してみてはどうでしょう。お客さんには長靴を貸し出し、その長靴も何色か用意する。傘も面白いデザインや派手な傘を準備して散歩する企画です。まさに「雨の日だからこそ」の振る舞いがあるのではないでしょうか。天気の良い日のプログラムはたくさん用意していますが、曇天や小雨、大雨のプログラム開発はおろそかです。全ての天候でのあらゆる振る舞いを考えてみる必要があるようです。
国内には10万カ所以上の数の都市公園がありますが、その多くは近隣公園規模(約2ha)以下の公園です。500㎡以下の小公園もたくさんあります。むしろ私たちが日常目にするのはそうした小公園でしょう。「ベストポケットパーク」という表現もありますが、たとえ小さくとも景色として地域になじんでいる公園は宝です。その公園で絵を描く、写真を撮るなど、その公園ならではの振る舞いが起きるようにしたいものです。小公園の活用は、管理者の目線では難しいことが多いものです。また、役所だけで考えていても現場は動かない。地域と一緒に、公園観察学を通した活動がいいと思います。都心の公園文化についても考えてみましょう。例えば、これも私達がマネジメントしている「新宿中央公園」を例にとると、路上生活者がクローズアップされます。路上生活者は一般的には歓迎されませんが、都心の公園ならではの一種の振る舞いであり、近くに歓楽街があり、不特定多数の人の流れがある都心の公園の文化としての捉え方が成り立ちます。
逆に、地方都市の公園文化にも注目してみましょう。先日の日経新聞ランキングで、西日本で1位にランクされた熊本市の「水前寺江津湖公園」は、人口73万の大都市型ありながら、公園成立の歴史と伝統から、地域住民と密着した公園として知られ、独自の公園文化が伝えられ、育まれ、そして新たな文化を生み出しています。
何はともあれ、公園はすべて地域生まれであるから地域を映し出す鏡でありたいですね。と同時に公園文化はグローバルな評価を受けやすいものです。小公園―大公園、都会型―地方型と言った公園の違いによる公園文化を一つ一つ追うことでまた一歩公園の価値向上が進むのではないでしょうか。
※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。2014年7月掲載

33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂
32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純
31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳
30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明
29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高
28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望
27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼
26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一
25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子
24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子
23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗
22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理
21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人
20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表
19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子
18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真
17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子
16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子
15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣
14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)
13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹
12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二
11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳
10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史
09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司
08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子
07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和
06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信
05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋
04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八
03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平
02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝
01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎


































