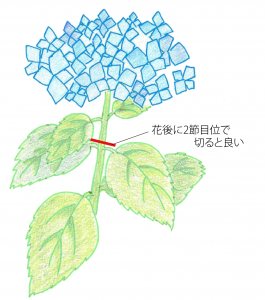千葉県生まれ。1級造園施工管理技士、公園管理運営士。国営讃岐まんのう公園 管理センター副管理センター長。(財)公園緑地管理財団(現在の(一財)公園財団)本部で緑や公園利用の普及に関する業務や国営讃岐まんのう公園、木曽三川公園等の大規模公園の維持管理、運営管理に携わる。平成25年4月より現職。

アジサイの多くは、土が酸性であれば「青色」になり、中性~弱アルカリ性であれば「ピンク色」になるといわれています。そのため、青い品種のアジサイを中性~弱アルカリ性の土に植えると、紫色に変化してしまいます。
それは、土中のアルミニウムが影響しているといわれています。酸性の土壌では土中のアルミニウムが水分に溶けやすいので植物の根からアルミニウムが吸収され、アジサイの細胞内のアントシアニン色素(※)等に作用して青くなります。アルカリ性ではアルミニウムが溶けず吸収されないため青色が発色せずに、アントシアニン色素の本来の色である赤みを帯びるようです。
土を酸性にしたいときは、酸度無調整ピートモスなどを土に混ぜて調整するとよいでしょう。また、肥料はカリ分の多いものがよく、リン酸分が多い肥料は施さないようにしましょう。
アジサイは別名「七変化」とも呼ばれています。同じ場所にあっても白、赤、紫、青と多様な色合いを見せてくれるアジサイの群生はとても美しいものです。変化に富んだ豊かな花のグラデーションを存分に楽しめるのもアジサイの魅力のひとつではないでしょうか。
※
アントシアニンは、橙赤、赤、紫、青、水色と幅広い花色をもたらす色素です。アジサイで青を発色させるためには、
①アントシアニンがある
②補助色素(助色素:無色の有機酸の一種)がある
③アルミニウムを根から吸収できる
という3条件が少なくとも必要といわれています。きれいな青いアジサイが欲しい場合は、青色になる性質を持った花をまずは選ぶ必要があります。もし手持ちのピンク色のアジサイを青色にしようとして、土壌を酸性に変えたとしても、青色になるとは限りません。補助色素を持っていないか十分でない、または持っていても働きが阻害されるなど正常に機能しない場合は、ピンクのままか紫となり、きれいな青にはならないようです。また、白色のアジサイにはアントシアニン色素そのものがないようです。品種や土壌等の環境によって微妙に異なるアジサイの色に関わる複雑なメカニズムは、まだ十分には分かっていないところがあります。
剪定方法の視点から、管理しやすいアメリカアジサイ「アナベル」をご紹介したいと思います。
また、アナベルの花は、白色、そして徐々に緑色へ変化します。これは花の中の色素が分解されて起こる老化現象の一種です。
アジサイは極端な乾燥に弱いです。日当たりがよいところ~半日蔭でよく育ちますが、乾燥には注意しましょう。アジサイの学名に含まれる「Hydrangea(ハイドランジア)」は「水の器」を意味していていることからも、水を好むことがわかります。
西日の当たる場所は乾燥しやすいため、鉢植えの置き場や庭に植える場所を決める際に気をつけてください。また、夏場の日当たりがよく乾燥しやすい場所でも楽しみたい場合は、アジサイの株のまわりに藁などを敷くマルチングを行うとよいでしょう。
今年のまんのう公園のアジサイは十分に育ち、40種2万株のアジサイが6月中旬から見頃となっています。公園では「あじさいまつり」(6/13~7/5)として、野点、アジサイにちなんだクラフト、アジサイの剪定教室、アートパラソル作りなどのイベントを実施しています。
また、ビジターセンターでは「アジサイとシーボルト展」も開催しています。“ハイドランジア”として色や形ともバラエティ豊かになった今日のアジサイは、シーボルトによるヨーロッパでの紹介がきっかけのひとつとして知られています。その歴史や品種をパネルで展示しつつ、アジサイ苑ではシーボルトにまつわる品種を植栽しています。
なお、エントランスでは、暑さ対策として香川伝統工芸品の「高松和傘(絵日傘)」や、雨の中でも楽しめるよう、雨に濡れると色が変わる楽しい雨傘を貸し出しています。梅雨のひと時、華やかなアジサイとアジサイにまつわるイベントを楽しみに、是非まんのう公園にご来園ください。
国営讃岐まんのう公園 http://www.mannoukouen.go.jp/